「BTS(防弾少年団)現象」とは、BTSとファン「ARMY(アーミー)」による驚くべき社会的・文化的な変化だ。この現象は、美学的でありながら、多分に政治的でもある。急激に変化しつつある現在のメディア環境を芸術の創作、発信、再生産に積極的に活用することで生まれたものだ。
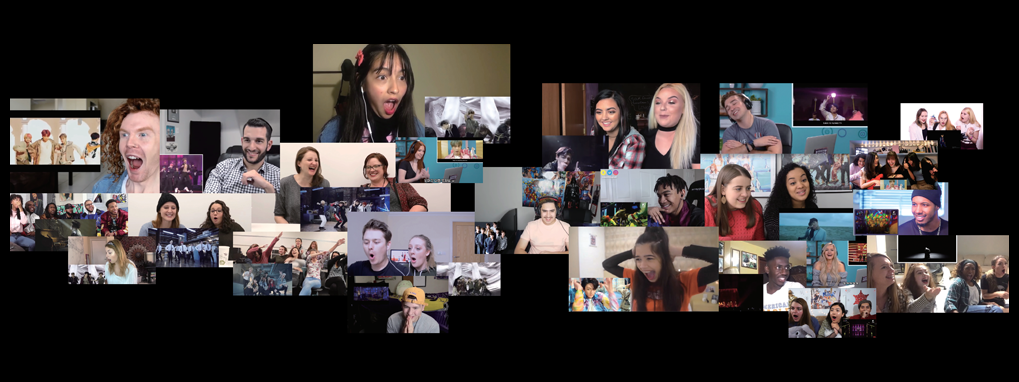
世界各国のBTSファンは、様々なオンラインメディアでBTSの映像を見て、リアクションビデオを作ってソーシャルメディアに投稿する。BTSの映像は、ファンによってデジタルネットワーク上で活発に再生産・流通されている。
BTS(防弾少年団)はミュージシャンなので、現在のこの意味深い現象を把握する上で、彼らの音楽、パフォーマンス、メッセージは欠かすことができない要素だ。しかし、彼らが素晴らしい音楽を作る才能豊かで魅力的な歌手だというだけでは、この現象を十分に理解・説明できないのも事実だ。BTSと世界中のファンを出合わせて強く結び付ける基盤と、その基盤に含まれている方向性、そして大衆が熱望する変化の方向性が一致するポイントまで考えなければ、この特別な現象の意味をはっきりと説明することはできない。
そこで最も重要なのは「BTS現象」の中核的な要因に共通する「水平性」だ。水平性は、デジタルネットワークという技術が持つ本質的な属性だ。資本と権力を中心に形成された位階(序列)によって水平性を取り込もうとしないBTSのコンテンツ、より水平的な世界を求める彼らのメッセージ、さらに階級、人種、言語、ジェンダー、文化、宗教など様々な領域で噴出している水平性への大衆の熱望、そのような熱望を持つファンとBTSとの水平的な出会い、そうした点について考えてみる必要がある。
特に変化の方向性をはっきりと知る手がかりは、芸術の受容者、消費者、ファン、あるいは観客ともいえる大衆の変化に見出すことができる。なぜならBTS現象の核心は、世界の多くのファンの熱狂の裏にある政治的な無意識や時代精神とも関係しているからだ。
流動する観客
BTSのミュージックビデオ、オンライン・インスタレーション映像、娯楽コンテンツ、舞台映像などを享受する観客のメディア環境は、非常に多様なスクリーンとネットワークで構成されている。その中でオンライン・インスタレーション映像は、BTSが公開した映像のうちショートフィルム、ハイライトリール、トレーラーなどの名で流通している映像の総称だ。ミュージックビデオや映画のような既存のカテゴリーでは単純に分類できない映像で、まるでギャラリーに設置された映像作品のように間隔を置いて設置される。ただし、空間的な間隔ではなくて時間的な間隔を置いて、オフラインのギャラリーではなくオンライン空間で公開されている。その短編映像の象徴的なイメージと叙事は、他のミュージックビデオと参照し合いながら、多彩な意味の系列を生み出す。実験映画、短編映画、ビデオアートにも近いそれらの映像は、BTS映像の特徴の一つといえる。
BTSは、このように時代の流れと共に発展してきた技術的な基盤の上で、膨大な量のコンテンツを生産している。特に「防弾世界観(BTS Universe)」といえるミュージックビデオ、オンライン・インスタレーション映像などは参照し合う構造にあり、多彩な解釈のできる象徴的なイメージを積極的に活用している。そして、そのような映像は、デジタルネットワーク上での観客の自由な接続や活用を前提にしている。数多くの映像コンテンツをマルチプラットホーム環境で消費する観客は、様々なプラットホームやモバイル機器を使って、移動中にも映像を見ることができる。さらにループ再生、拡大、色調補正、編集などの行為も自由に行える。そのような点で、彼らは「流動する観客」といえる。
BTS現象は、世界の変化と未来の方向性との関係性の中で、メディア基盤の芸術にどのような価値が求められているのか、メディア環境がどのような方向にエネルギーを強く表出しているのかという問いを私たちに投げかけている。

インスタグラムで「#BTS logo」と検索すると、全世界のファンによって加工されたBTSとARMYのロゴが数千件ヒットする。これはファンとスターのインタラクティブな関係を物語っている。
芸術の生産者と消費者の相互転換
観客は、そうした多彩なプラットホームから得た映像を自由につなげてリミックスを作り、一部を選んでクリップに加工する。また、自分のリアクションや解釈を映像に合わせてさらに多様なコンテンツを生産する。そのようにして生まれたコンテンツは、原材料に当たるBTSの映像と共に、ネットワーク上で共有される。こうした活動は、一部の限られたファンだけでなく、大多数のファンが日常的に行っている。多くの人にとって日常的なことに過ぎず、大したことではないと感じている。このような受容態度の変化が、芸術様式において根本的な変化をもたらしたといえる。
ドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンによると、大衆の受容態度の変化こそ、芸術様式の変化をもたらす最も根本的な要因だ。ベンヤミンは『複製技術時代の芸術作品』で「大衆は、芸術作品に対する従来の全ての態度を新しく生まれ変わらせる母体だ。量が質に転化した。芸術に参加する大衆の数的な増加は、参加方式を変えた」と述べている。ベンヤミンによると、特定の技術で実現される生産力の発達は、芸術の生産様式そのものを変化させる。技術の発達は、大衆が芸術受容に参加する方式を変化させ、それは芸術様式そのものの質的な変化を引き起こす。
作品生産の参加者として観客の態度を変化させた根源的な技術基盤は、オンラインネットワーク・プラットホームだ。オンラインで公開される映像は、観客のストリーミングや共有によって、その存在の方式と役割が決まる。オンライン上に存在する映像は、劇場の上映映画やDVDの映画とは違って物質的な装置がないため、情報の形で存在し、観客のクリックや共有という行為によって現実化する。このような技術基盤の変化による観客参加という構造が、BTSの映像においてますます顕著になっている。観客が作り出す映像は、BTSがアップロードする映像と同じプラットホーム上でつながり合い、多様な意味を生み出している。
今や作品の範囲や領域に存在するのは、アーティストの生産したものに限らない。観客が作った作品も、アーティストの映像の意味を拡張・再生産し、共に流動的な作品の領域を生み出している。作品の意味と使い方は、イメージのネットワークの中で絶え間なく再規定・再創造され、新しく配置されていく。そうした配置は、多彩な機器が使用者・観客の行為の中に統合される、ある種の融合過程だといえる。それはヘンリー・ジェンキンスが『Convergence Culture :
Where Old and New Media Collide (収束する文化:古いメディアと新しいメディアの衝突)』で述べたように「一つの機器に様々なメディア機能を統合させる技術的な過程ではなく、消費者が自ら新しい情報を探し、点在しているメディアコンテンツをつなげようとする文化的転換」だといえる。
そうした作品の生産方式では、芸術家と観客、芸術の生産者と消費者の境界がかつてないほど急速に薄れていく。伝統的な芸術概念における芸術家の超越的な地位、権威、役割も維持できない。観客はオンラインネットワークを基盤にして作品と関係を結び、共に芸術の創作過程に参加して、同等な使用者としてその中で新しい意味を生成する。つまり、芸術の概念や性格が変化する状況に置かれているのだ。

「ARMYPEDIA(アーミーペディア)」は2019年2月25日から1カ月間、現代自動車とBTSが行ったキャンペーン。全世界のARMYが、ARMYPEDIAのホームページにBTSに関する文、写真、映像などをアップロードした。英国ロンドンのピカデリーサーカスの街頭ビジョンⓒ 現代自動車
共有価値
ネットワーク上の新しい映像芸術は、作品の流動的な範囲、映像のネットワークによる開かれた作品環境の形成、伝統的な芸術家と受容者の境界の崩壊、モバイルネットワーク技術を基盤とする流動的な観客の現実的な移動性などを特徴としている。私はそれを著書『BTS芸術革命』で「ネットワークイメージ」と名付けた。
そうした特徴は、共有プラットホームやソーシャルネットワークで日常的に行われている観客の行為を基盤としている。モバイルネットワーク基盤のSNSと共有プラットホームの社会的な掌握力、そのサービスを日常的に使う絶対多数の観客を考慮すれば、21世紀のモバイルネットワーク社会が、この新しい芸術形式・ネットワークイメージに求めるのは「共有価値」だろう。
ヴァルター・ベンヤミンが述べたように、複製技術の登場によって芸術の価値が「礼拝的価値」から「展示的価値」にシフトしたように、モバイルネットワーク技術の全面化によって21世紀の芸術の価値は「展示的価値」から「共有的価値」にシフトしている。ネットワークイメージという新しい芸術形式の登場が、単に芸術形式の変化を意味すると考えてはいけない。それは、巨大な世界史的変革の表現という根源的な意味を持っている。つまり、世界の変化が進んでいる方向性の兆候的な表現なのだ。
BTS現象は、単に人気ボーイズグループの少し特別なミュージックビデオの活用にとどまるものではない。このような驚くべき現象は、世界の変化と未来の方向性との関係性の中で、メディア基盤の芸術にどのような価値が求められているのか、メディア環境がどのような方向にエネルギーを強く表出しているのかという問いを私たちに投げかけている。